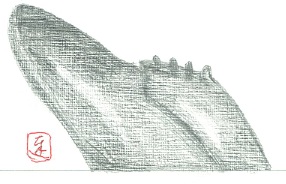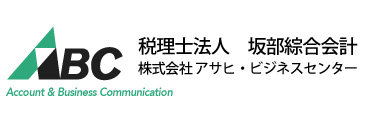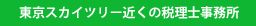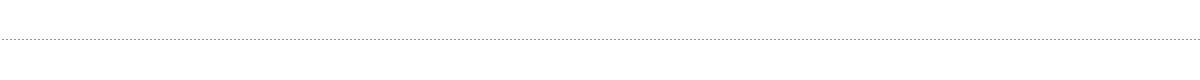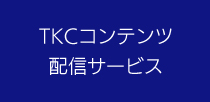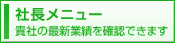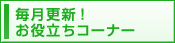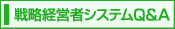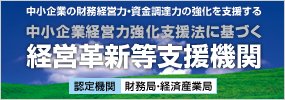ABCネットニュースNETNEWS
(発行日 2025年9月12日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
本棚の奥にあった本をふと手にとって見てみると、いままでぼんやりしていた記述がフォーカスされて目に飛び込んでくることがあります。その本は、「GOLF300ヤードの法則」(若林貞夫ゴルフダイジェスト社2008年1月)というタイトルの本です。ゴルフを嗜まれる方は、お分かりだと思うのですが、ゴルフではあの小さな球を、棒の先についた鉄の板で打って、はるか先まで飛ばす必要があります。まっすぐ、遠くへ飛ばしたいのです。若林プロ(2008年没)が、提唱したZ打法というテクニックの核心は、「体を同じ方向に回さずに、腰を切り上げつつ、手で突く。」ということにあります。17年前にこの本を読んでも理解できず、やることもせず、体をまわすボディターンが正しいと思い込んでゴルフを続けてきました。他にも同じようなことがあります。例えば、絵は「しっかり見て、ゆっくり書く」。書は「筆の元まで墨をつけて書く」とちょっとしたことに気づかず、なんと無為な時間を過ごしたことか。とはいえ、この気づきは、踏ん張って自分と向き合い続けることに対するご褒美のような気がします。
今月のトピックス
【不定期連載】労働者を雇ったら知っておくべきこと ~ ⑧産前産後休業 ~ |
特定社会保険労務士 喜志 久美子
1.はじめに
少子高齢化と言われて久しく、とうとう人口が減り始めた日本ですが、少しでも子育てしやすい環境をと、出産・育児関連の制度は改正を重ねています。今回は産前産後休業について基本的なポイントをまとめてみます。
2.産前産後休業
(1) 産前休業
労働基準法では、「6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産をする予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」とあります。つまり、原則として出産予定日の6週間(42日)前から産休に入ることはできますが、本人が希望する場合は出産の直前まで働くことも可能です。ただし、男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置により、「医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を講じなければならない」とされていますので、個々の状況に応じて対応しなければなりません。
出産日は産前休業の最終日となります。
(2) 産後休業
産前は本人の請求がなければ就業禁止にはなりませんが、産後については「産後8週間(56日)を経過しない女性を就業させてはならない」とありますので、本人が希望しても原則として就業させることはできません。ただし、産後6週間を経過した女性について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。
3.出産に関する給付金
(1) 健康保険出産育児一時金
被保険者及びその被扶養者の出産に関する費用の補てんとして給付されるものです。産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合には、1児につき50万円が給付されます。(産科医療補償制度に未加入の医療機関等もしくは妊娠週数22週未満での出産の場合は1児につき48.8万円)
現在は、出産前に医療機関との「合意文書」を交わすことで利用できる「直接支払制度」が主流となり、病院での支払いは不足分のみ、給付額以内であれば支払は不要(差額は後日請求可能)とすることができます。
一定の要件により、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも給付が受けられます。
※出産費用については、2026年度をめどに自己負担の無償化、保険適用の対象(現在は非対象)等も視野に議論が始まっています。
(2) 健康保険出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み報酬が受けられない場合に、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養が取れるように設けられている制度です。原則として、出産日(もしくは予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日後56日目までの期間について支給されます。支給額(1日あたりの額)は、【支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)となります。
一定の要件により資格喪失後の継続給付が可能です。
4.社会保険料免除
出産日(もしくは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)、出産日後56日のうち、実際に休んだ期間については、健康保険(介護保険含む)および厚生年金保険料は事業主の申し出により被保険者(本人)分・事業主分とも免除されます。
5.産休前の傷病休職について
妊娠期間中に悪阻(つわり)等により体調を崩し就業できない場合は、医師の証明を受けることができれば傷病手当金を受給することも可能です(支給額は出産手当金と同じ計算方法です)。例えば、産休開始日(出産予定日の42日前)の前から体調不良で就業が困難な状態のため2ヶ月ほど早く休職に入った場合、社会保険料免除は受けられませんが、その2ヶ月間は傷病手当金を受けることができます。ただし、その後予定日より1ヶ月早く出産した場合は、産休期間が1ヶ月前倒しになりますので、前倒しの期間は産休期間となり社会保険料も遡って免除とすることができます。なお、傷病手当金と出産手当金の期間が重なる場合は出産手当金のみが支給されることになります。
6.産後パパ育休(出生時育児休業)
通常の育児休業とは別に、原則として子の出生後8週間(女性の産後休業期間)のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。出産後のサポートや実家に帰省する場合の送り迎え等のためと考えるとイメージしやすいと思います。主に配偶者が出産をした男性が対象となりますが、養子を養育している女性も対象となります。
7.おわりに
育児・介護休業法の改正により、令和7年10月1日からは、妊娠・出産等の申出時に「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取」が義務づけられました。詳細は省略しますが、対象者がいる場合はご確認のうえご対応をお願いいたします。
|
|
|
|
|
私のオススメ 「 CAPIC製品 」
 |
 |
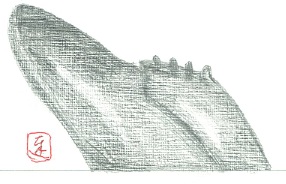 |
新宿駅構内で「キャピック展 展示即売会」というイベントを見かけました。わかりやすく言うと刑務所作業製品の展示即売会ですが、「CAPIC(キャピック)」というのはブランド名で、刑務所作業製品の材料提供や販売を行う公益法人が商標登録したものです。展示品は家具などの木工製品、靴や鞄などの革製品が目立ちました。家具は高いもので数十万円、靴は1万円前後と安くはありませんので購入まではしませんでしたが、高品質なのかもしれませんので次に見かけたら靴くらいは購入してみようかと思いました。ちなみに売上は事業運営上の費用と国庫納入金に充てられるそうで受刑者の収入になるわけではないようです。
CAPICとは | CAPIC ~キャピック 心をこめた 手づくりの逸品~
|
あとがき
大阪万博に行ってきた。覚悟はしていたが猛烈な暑さだった。入場口やパビリオンだけでなくお土産を売っているお店まで大行列だったが、あちこちに「貸し日傘」が設置してあり、初めて使用したであろう男性がその効果に感動している様子を何度か見かけた。最新技術を体験する万博で日傘とは・・これもまた素敵。(喜志)