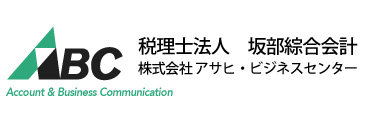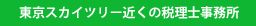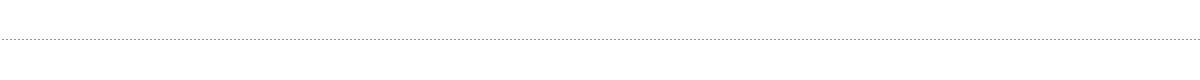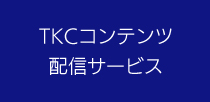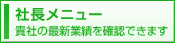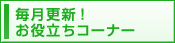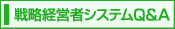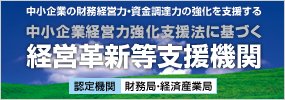ABCネットニュースNETNEWS
(発行日 2025年8月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
千住博氏(日本画家「滝や崖」をテーマとしたシリーズが有名。京都芸術大学の元学長)の著書「芸術とはなにか」に、興味深い記述があったのでご紹介します。著名な絵画の右隅(原則)を見ると、サインなり雅号(がごう)が入った赤枠で押印しているのを見ることがあります。これがいわゆる「落款(らっかん)」というもので、作者の「完成品」という意思表示であり、贋作(がんさく)防止という意味合いもあるようです。
ここから先は、千住氏の興味深いコメントです。「落款の入った作品が何百年も残るためには、『歴史の審判』というフィルターを通らなければならないし、そういう意味で落款は、『渡世的浮世の義理』に過ぎない。」そんな目で落款を見たことはありませんが、これが芸術家の視点なんでしょうね。
今月のトピックス
令和7年度税制改正 (2) |
飯岡 千瑛
令和7年の税制改正について、今回は「年収の壁」の見直しに焦点を当てて解説します。
1.年収の壁とは
所得税において、基礎控除48万円+給与所得控除(の最低額)55万円=103万円となるため、給与収入が年間103万円以内であれば所得税の納税額が0円となります。また扶養控除を適用できる控除対象扶養親族に該当するための要件に合計所得金額48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)が含まれるため、給与収入年額103万円を超えると「本人の所得税の納税の発生」と「扶養者の所得税の納税金額の増加」の二か所で所得税負担が上がることになります。そのため、給与の手取り額の確保を目的として年間給与収入が103万円を超えないように調整している、という問題がありました。
2.令和7年の税制改正について
令和7年より、基礎控除の金額は合計所得金額132万円以下の場合95万円に、132万円超2,350万円以下の場合は58万円に引上げられ、給与収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除の金額は65万円に引上げられました。従前と同様に計算すると、基礎控除95万円+給与所得控除(の最低額)65万円=160万円となります。
基礎控除の引上げに合わせて控除対象扶養親族の合計所得金額要件も58万円に引上げられました。
また生計を一にする19歳以上23歳未満の子や孫など一定の親族(特定親族)の合計所得が58万円を超えても所得控除を受けられるように、特定親族特別控除が創設されました。
ただし、源泉徴収事務の変更は令和7年11月まで生じず、令和7年分に関しては年末調整での減税となるため、令和7年11月までの月次給与に関しては従前同様に源泉所得税が徴収されます。
3.所得税計算の具体例①
自身の給与収入が年額900万円、扶養している17歳の子がアルバイトで年額120万円給与収入がある場合。
※社会保険料等は割愛します。
【従前】
子: 給与収入120万円 △給与所得控除55万円 △基礎控除48万円 = 17万円
⇒ 17万円 × 所得税率5% = 年税額0.85万円
(合計所得金額65万円 ⇒ 控除対象扶養親族の要件を満たさない)
自身: 給与収入900万円 △給与所得控除195万円 △基礎控除48万円 = 657万円
⇒ 657万円 × 所得税率20% △42.75万円 = 年税額88.65万円
【令和7年以後】
子: 給与収入120万円 △給与所得控除65万円 △基礎控除95万円 ⇒ 納税なし
(合計所得金額55万円 ⇒ 控除対象扶養親族に該当する)
自身: 給与収入900万円 △給与所得控除195万円 △扶養控除38万円 △基礎控除58万円 = 609万円
⇒ 609万円 × 所得税率20% △42.75万円 = 年税額79.05万円
4.所得税計算の具体例②
自身の給与収入が年額900万円、扶養している20歳の子がアルバイトで年額150万円給与収入がある場合。
※社会保険料等は割愛します。
【従前】
子: 給与収入150万円 △給与所得控除55万円 △基礎控除48万円 = 47万円
⇒ 47万円 × 所得税率5% = 年税額2.35万円
(合計所得金額95万円⇒控除対象扶養親族(特定扶養控除)の要件を満たさない)
自身: 給与収入900万円 △給与所得控除195万円 △基礎控除48万円 = 657万円
⇒ 657万円 × 所得税率20% △42.75万円 = 年税額88.65万円
【令和7年以後】
子: 給与収入150万円 △給与所得控除65万円 △基礎控除95万円 ⇒ 納税なし
(合計所得金額85万円⇒特定親族特別控除に該当する)
自身: 給与収入900万円 △給与所得控除195万円 △特定親族特別控除63万円 △基礎控除58万円 = 584万円
⇒ 584万円 × 所得税率20% △42.75万円 = 年税額74.05万円
5.住民税、社会保険の観点
多くの自治体では住民税の非課税限度額は45万円です。令和7年の給与所得控除の増額を加味した場合、給与収入が年額110万円を超えると住民税が課税されます。令和7年の収入に基づいて計算される、令和8年度分の住民税から適用となります。
今回は社会保険への加入要件は変更されていません。年収106万円以上の他いくつかの要件を満たす場合、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が発生します。また年収130万円以上で上記社会保険に加入していない場合、国民年金・国民健康保険への加入義務が発生します。
6.まとめ
令和7年の税制改正で所得税のかからない範囲が拡大しています。さらに扶養控除等も拡充されましたが、その分年末調整や確定申告でのチェック項目が複雑化しています。
また、給与収入の手取り額に関しては、所得税だけでなく住民税の課税要件や社会保険の加入要件も忘れずにご確認ください。
|
|
|
|
|
私のオススメ 「 迎賓館赤坂離宮 」
 |
 |
 |
四ツ谷駅から徒歩7分ほどの迎賓館赤坂離宮をご紹介します。
都心の一等地に建つヨーロッパ宮殿の様な外観の本館は、日本で唯一のネオ・バロック様式で国宝にも指定されています。そして豪華絢爛な内装は、天井の絵画、800㎏もあるシャンデリアやアンティーク家具などの非日常感と美術的価値に圧倒されます。部屋ごとにいるガイドの方の説明も楽しいので、是非聞いてみてください。本館と庭園は予約無しで見学でき、所要時間は1時間半から2時間位で入館料は1,500円。休館日は水曜日です。
※運営上の都合で、急遽「非公開」になる日もあるようですので、迎賓館赤坂離宮サイトの「公開日程」をご確認ください。
迎賓館赤坂離宮(内閣府)
https://www.geihinkan.go.jp/akasaka/
|
あとがき
4月から始まった自宅マンションの大規模修繕が先日終了した。足場が組まれていた約3ヶ月間は部屋のカーテンも開けられず窮屈な思いをしたが、マンション全体がキレイになり今はとても気持ちがいい。不満ばかり漏らしていた自分を反省するこの頃である。(喜志)