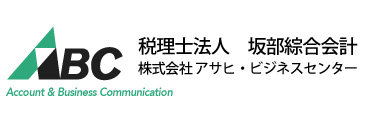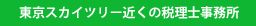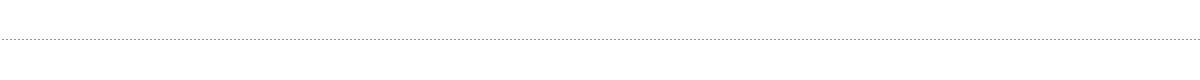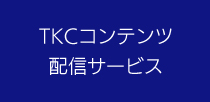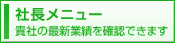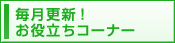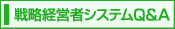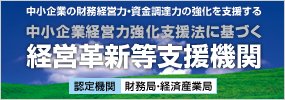会長コラムCOLUMN
第54回 「私の部下の育成観」 2025.4.30
どのような仕事にも、大事な勘所はあり、それをしっかり伝えるのが上司の役割となっています。未曽有の人材難にあって、企業も現存する人材の育成・教育研修に力を注いでいます。
組織の力、すなわち一人一人のパワーアップが、会社の戦略を実現する要であることは論を待ちません。ところで、研修を受け、知識で理論武装することが、社員の育成にどの程度効果があるのか。その評価は難しいところです。
私は、書道を少々(本当に少々です。)嗜んでいます。浅草橋に本部のある現代書道院の教室で、武田晃堂という先生について(運よく)学んでいます。ここでは、火・木の10:00~・14:00~・18:00~直接武田先生の指導を受けることができます。私のそれまでの感覚は、左にお手本をおいてそれをにらみながら臨書していくというものです。晃堂先生はそのお手本を私の目の前で書いてくれます。そのことをいうと晃堂先生は、さりげなく「これは、父(武田悦堂先生、書道界の草分けでもある。)の時代からの変わらぬ指導方針です。ご覧になって姿勢や運筆を見て取ってほしい。私も真剣に書きますので。」と仰います。
会社の人材育成には業務知識の修得はとても重要な事柄です。この知識をどのように業務に活かせるかということが重要な課題となります。つまり、業務知識と現場とをつなぐものを探る必要があるのです。ここは、諸々のご意見があると思いますが、私は、そのつなぐものを「経験」と考えています。
眼、耳、鼻、舌、身、意の六感、見て書いて手を使って悩んで身に着けたものは、知識とは一線を画するものです。個人的には、部下の育成には「経験7割」「知識3割」だと思っています。OJTはとても大切なのです。
茶道では、狭い茶室で主人に客がにじり寄って、そのお点前をじっと拝見し、クっと飲んで感想をいいます。実は、千利休以前の茶道は別室で点てたお茶を飲むというもので、今の相対するやり方(文化)が確立するまで続いたようです。師から弟子へ口伝するという形が取られる日本の伝統文化は、それほど古い歴史はないようです。
ところで、先輩が持っている技術やノウハウを引き継いでいくというのがとても重要なのですが、そんなに簡単に身につけられるものではないということはお分かりになると思います。では、「身につける方法」は何かというと、拍子抜けぐらいするくらい簡単で、「①毎日②真剣に③繰り返すこと」です(「物事の身につけ方」はいずれ稿を改めて一緒に考えていきたいと思っています。)
もちろん、世の中の事象をすべて経験できるわけではないので、その経験不足を補うものとして、想像力・仮説立案力・物事に対する配慮などが必要になるわけです。そのうえで、自分自身の本当の財産(宝)は、経験を積む機会を求める姿勢や願い、物事をありのままに見る習慣、自分のこととして考える(内省)習慣であることを肚に落としてもらえれば、部下の育成は自動化します。
二流のリーダーは事業や金を残す、一流のリーダーは人を残すといいますからね。